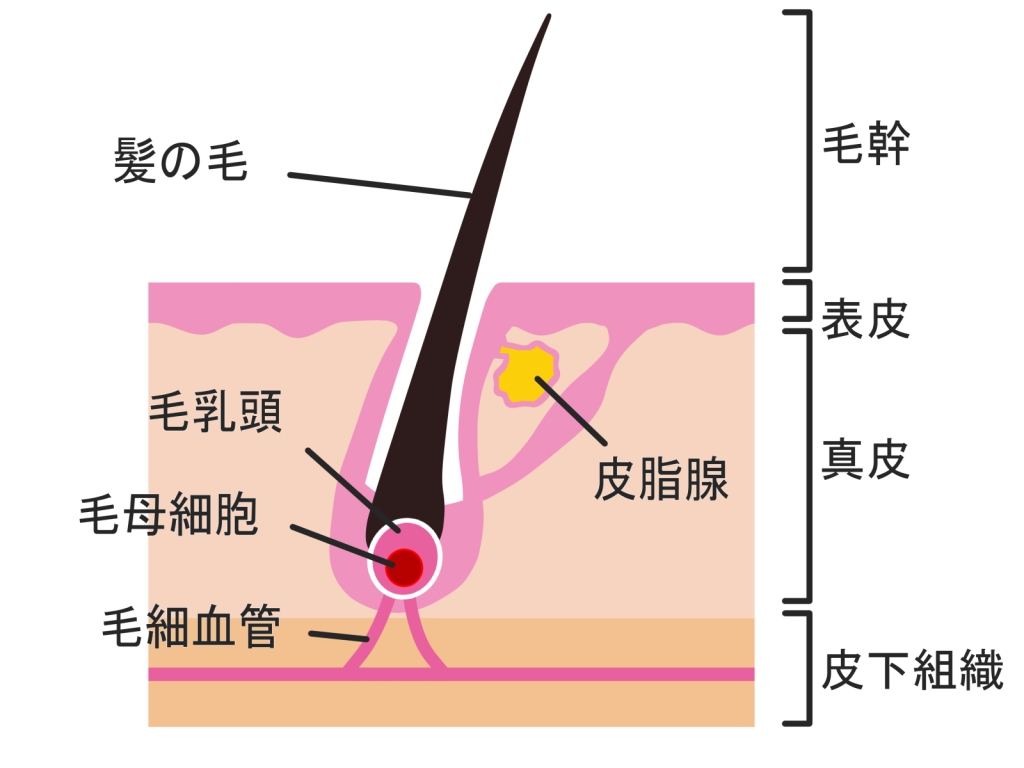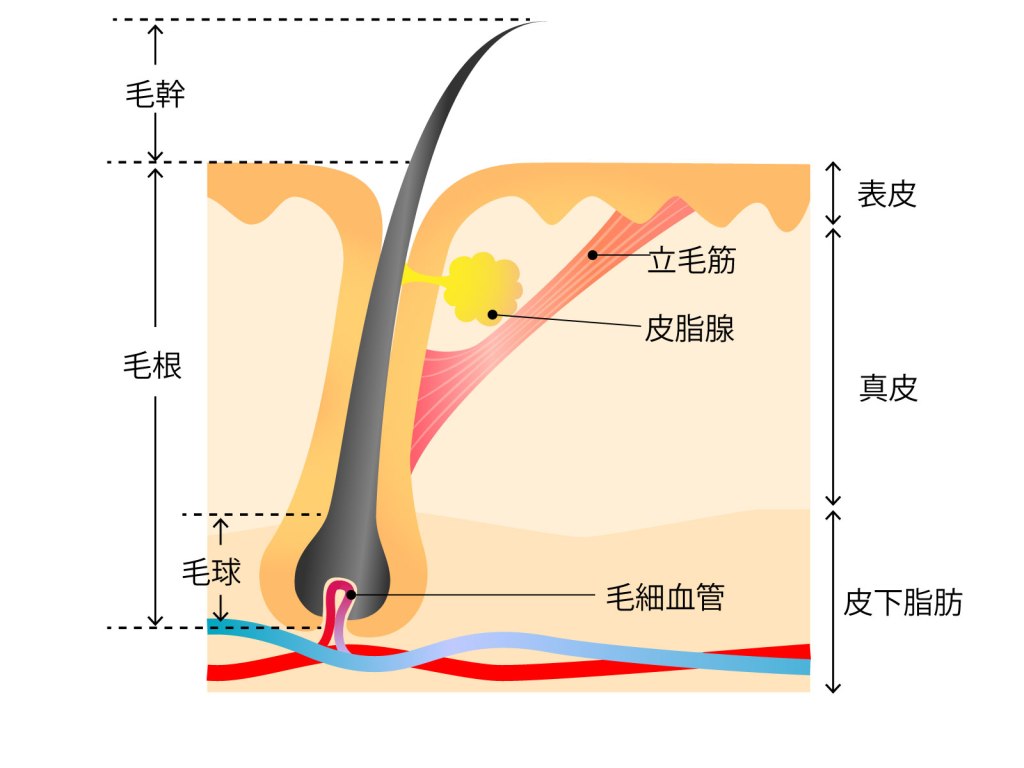登録販売者の2章は「人体の構造と医薬品」というテーマになります。
様々な人体の構造を「手引き」の文章だけでは理解しにくいので絵も交えて実際にどのように出題されるか見ていきましょう。

問題1 次の文章の正誤を判断してください。
歯冠の表面はエナメル質で覆われ、エナメル質の下には歯周組織と呼ばれる硬い骨状の組織があり、神経や血管が通る歯髄を取り囲んでいる。
この文章は、歯周組織ではなく正しくは象牙質になりますね。なのでこの文章は誤り
歯の絵が思い浮かべばすぐに答えることが出来ますが、「手引き」の文章だけでの理解は難しいですよね。
問題2 次の文章の正誤を判断してください。
歯冠の表面は象牙質で覆われ、象牙質の下にはエナメル質と呼ばれる硬い骨状の組織がある。
この文章も誤りになりますね。歯冠の表面がエナメル質でエナメル質の下に象牙質と呼ばれる硬い骨上の組織があるですね。
要するにエナメル質と象牙質の場所が理解できていれば問題なさそうです。
最後にもう1問
問題3 次の文章の正誤を判断してください。
歯の齲蝕とは、口腔内の常在細菌が脂質から産生する酸によって歯が脱灰されることで起こる歯の欠損のことであり、象牙質に達すると、神経が刺激されて、歯がしみたり痛みを感じるようになる。
これ四国エリアの問題です。常々四国エリアの問題は細かいところを突いてくるイメージがありました。
この文章は脂質が間違いで糖質ならば正解になりますね。
これで歯の問題は自信をもって答えましょう。