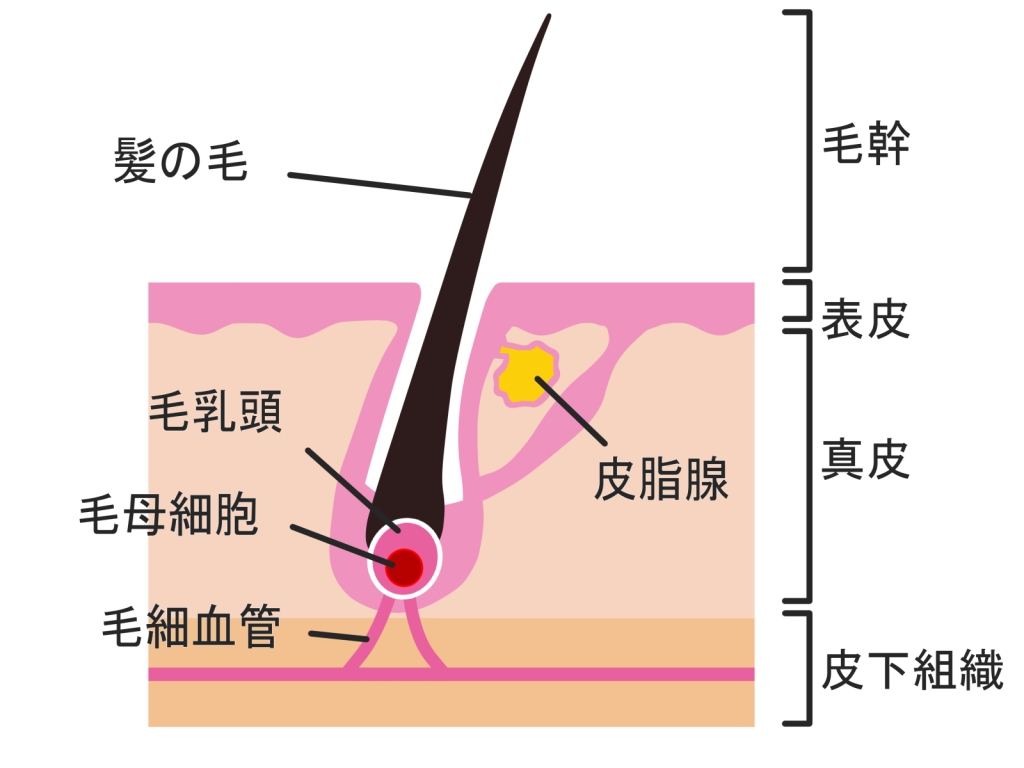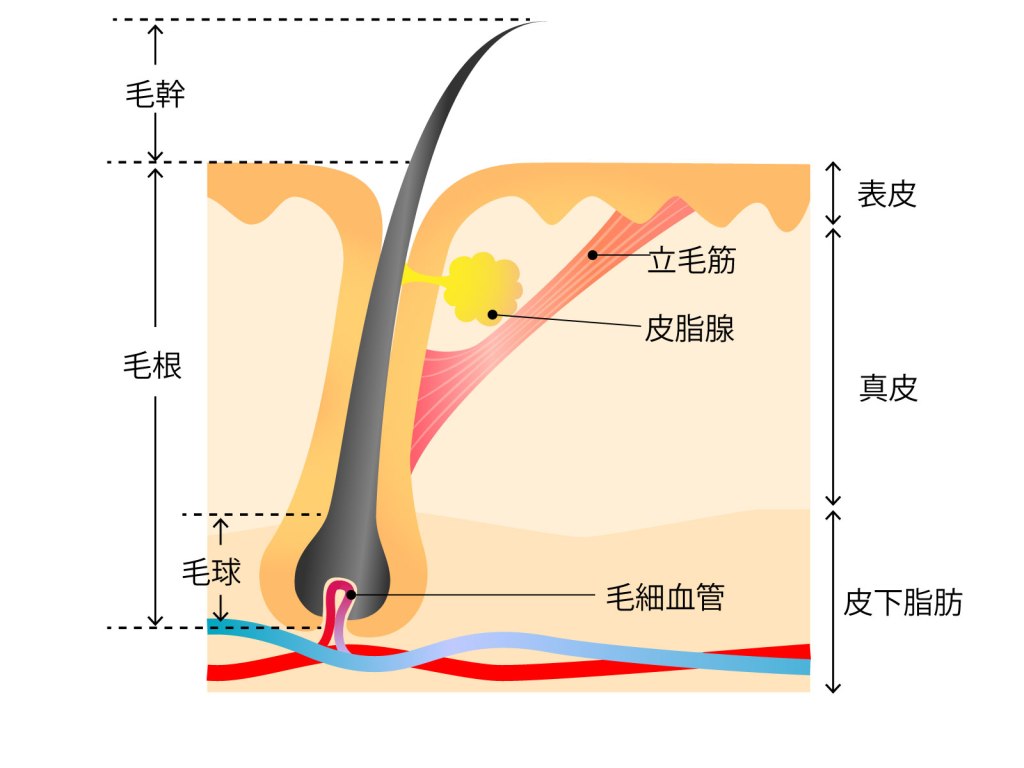店舗販売業をイメージはドラッグストアでいいと思います。

よく出題される問題で
店舗販売業において薬剤師がいれば調剤を行うことができる
といったものがあります。
しかし調剤は薬局でしか行うことができません。
最近は薬局併設のドラッグストアが出ていますが、それは店舗販売業とは別に薬局開設の許可を得ているからです。
ここ等辺を勘違いされる方がいらっしゃって、「ドラッグストアでも調剤してるじゃん!!」と質問されたりします。
たくさん勉強しているとごちゃごちゃになってくるので再度整理しておきましょう。
<a href="https://www.ac-illust.com/#a_aid=619a1c9f24dbc&a_bid=eb670aa9" target="_blank"><img src="//www.ac-associate.com/accounts/default1/banners/eb670aa9.jpg" alt="無料イラスト素材【イラストAC】" title="無料イラスト素材【イラストAC】" width="300" height="250" /></a><img style="border:0" src="https://acworks.postaffiliatepro.com/scripts/g5iueh?a_aid=619a1c9f24dbc&a_bid=eb670aa9" width="1" height="1" alt="" />